<第5回>「 母のもっていく思い出 」
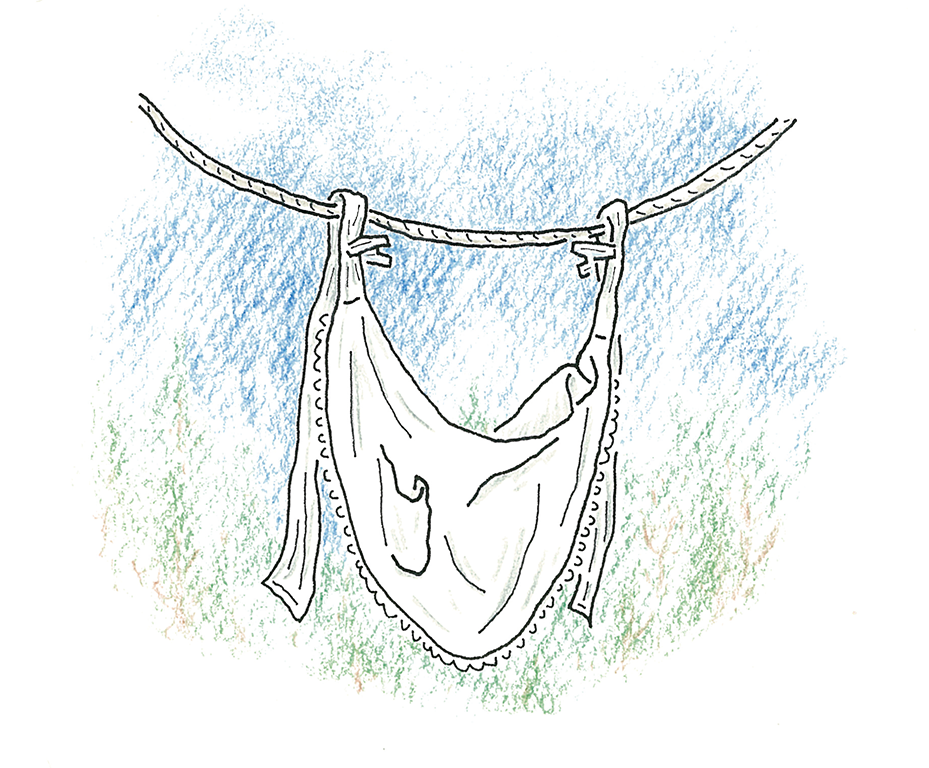
母は二度いなくなった。
と思う。
一度目はわたしが小学校へあがる前。
二度目はあがってまだ低学年の頃。
と思う。
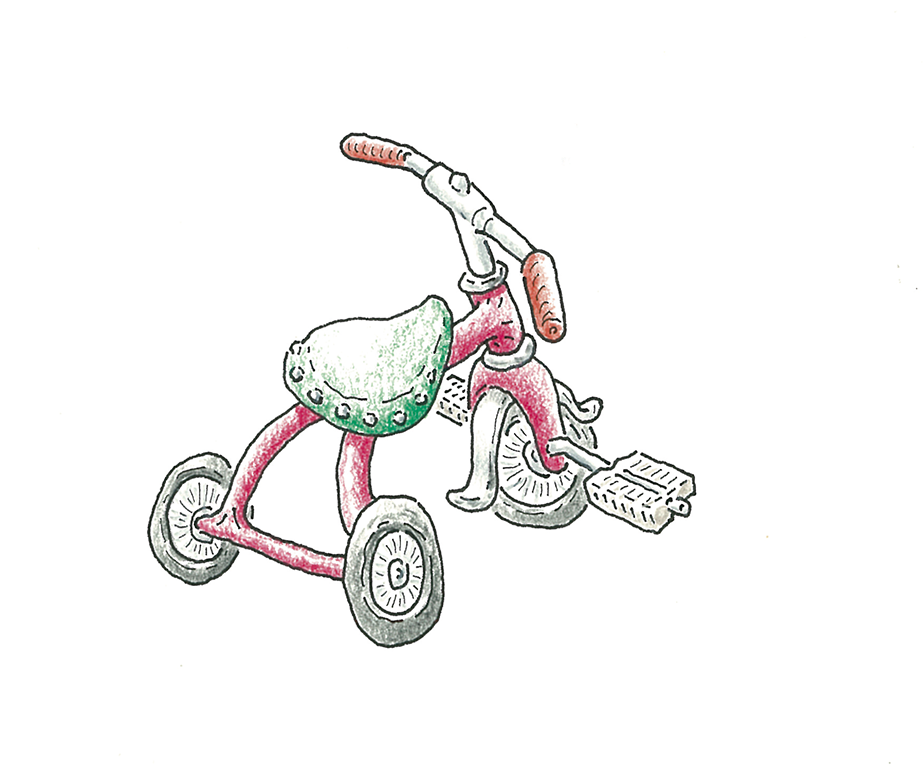
では、母の二十代と三十代に
それぞれ一度ずつか。
わたしの記憶にないだけで、
そう認識していないだけで、
実は三度目以降があったのかもしれない。
ほんの半日の、わずか数時間の小さなものも
たくさんあったのかもしれない。
一度目は家から母の姿が突然消えて、祖母が来た。
二度目は家から母の姿が突然消えて、誰も来なかった。
小学生の時は戸締まりをして登校できた。
どれほどの間、母はいなかったのだろう。
それは短くもあり長くもあり、確かな数字で憶えられていない。

悲しくなかったはずはなく、
さみしくなかったはずはない。
しかし、むしろその痛みよりも、
大きな不安を感じていた。
心細くて怖くて、
ぼんやりとどんよりと重い灰色の塊。
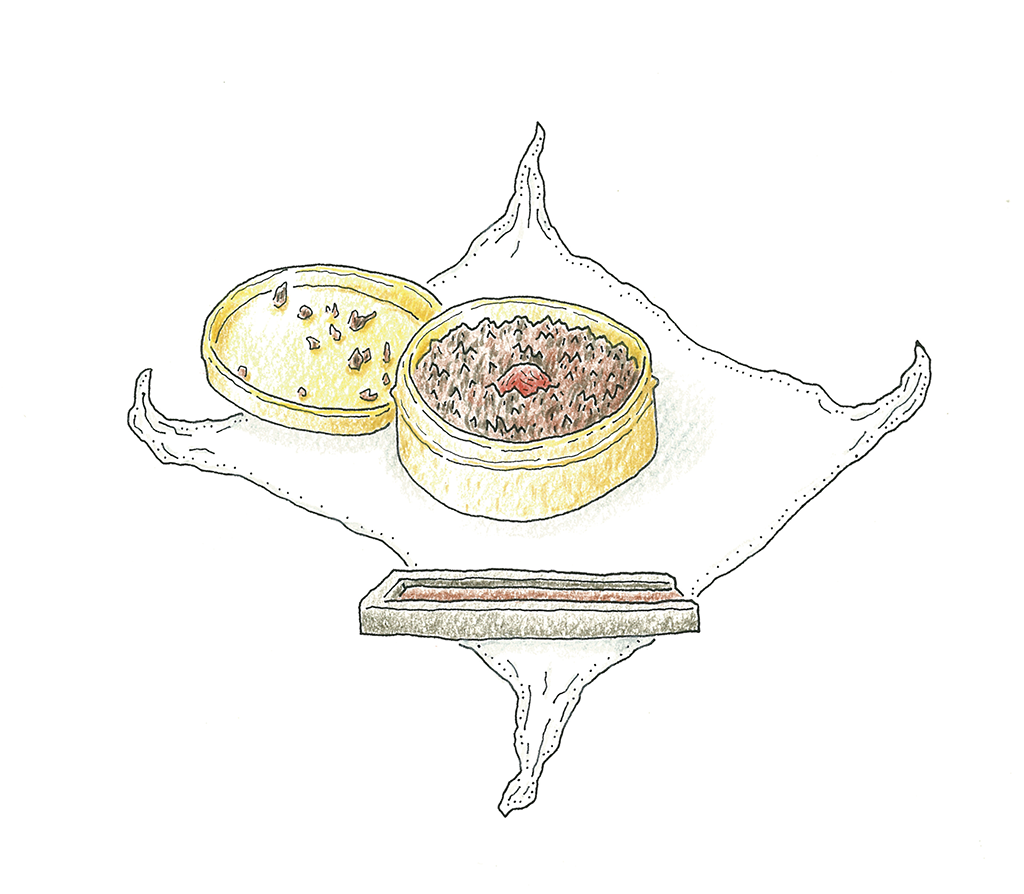
やって来た祖母はごはんつぶの上に
かつおぶしを敷き詰めた
アルマイトの弁当箱を
持たせてくれた。
おかずの方は思い出せなくて、
ごめんなさい。
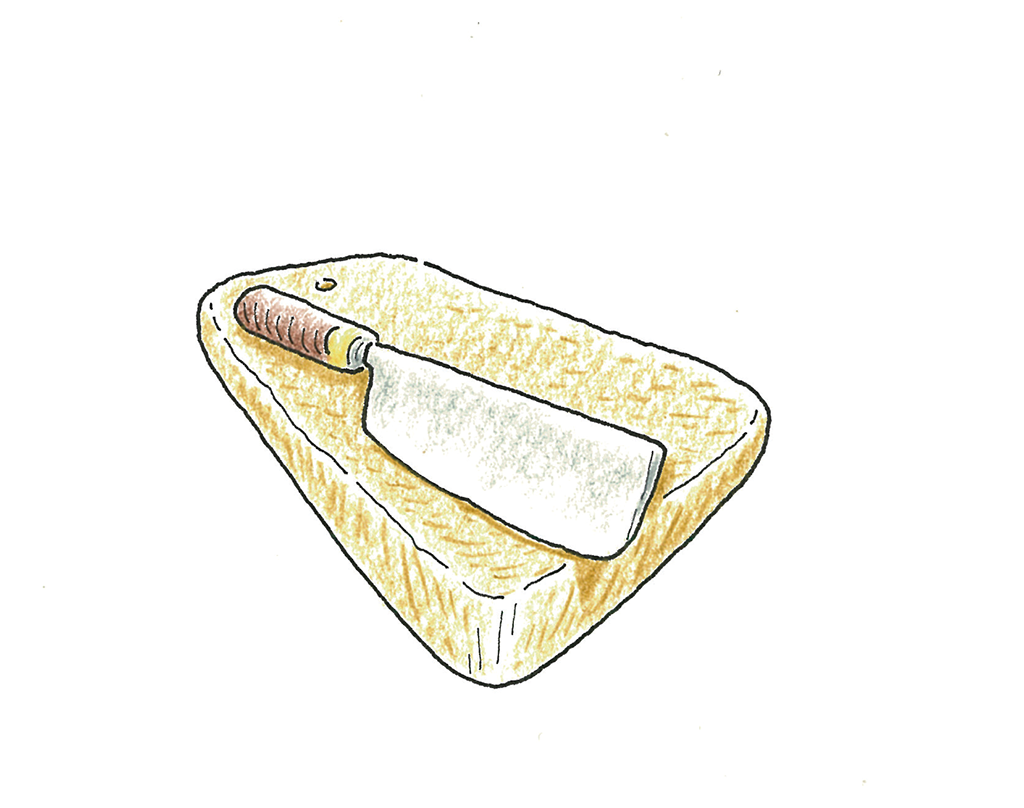
母は大事な用事で出かけて、
しばらく留守にしている。
わたしはそのような説明を
受けていたと思う。
それで単純なさみしさで済んでいた。
その時は。
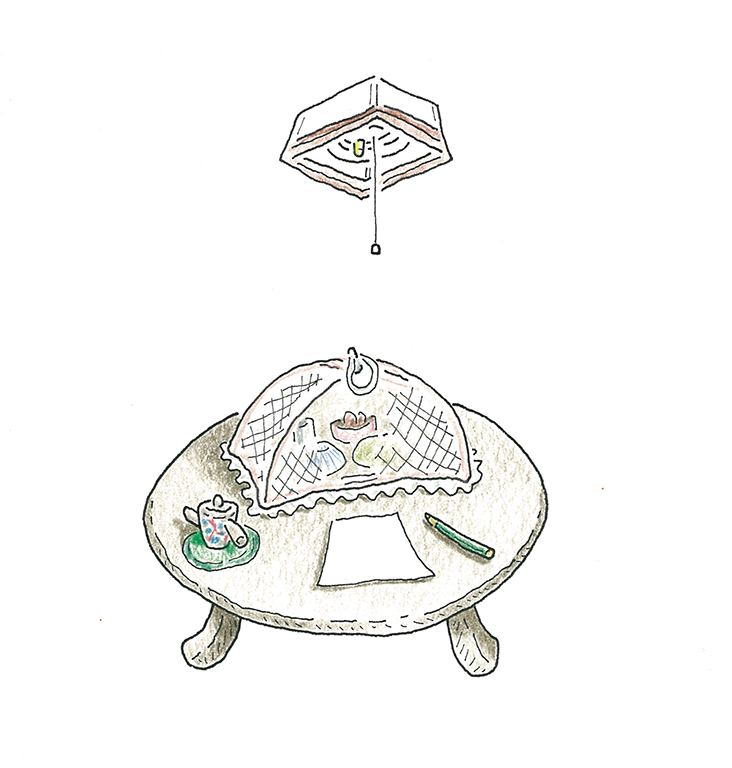
小学校から帰って来ると、
お膳の上に書き置きがあった。
文面はたいそうではなく、
体に氣をつけるようにとあった。
夕方になっても、
夜になっても、
母は戻らなかった。
電灯を点けたが、
ただ点いていただけだった。
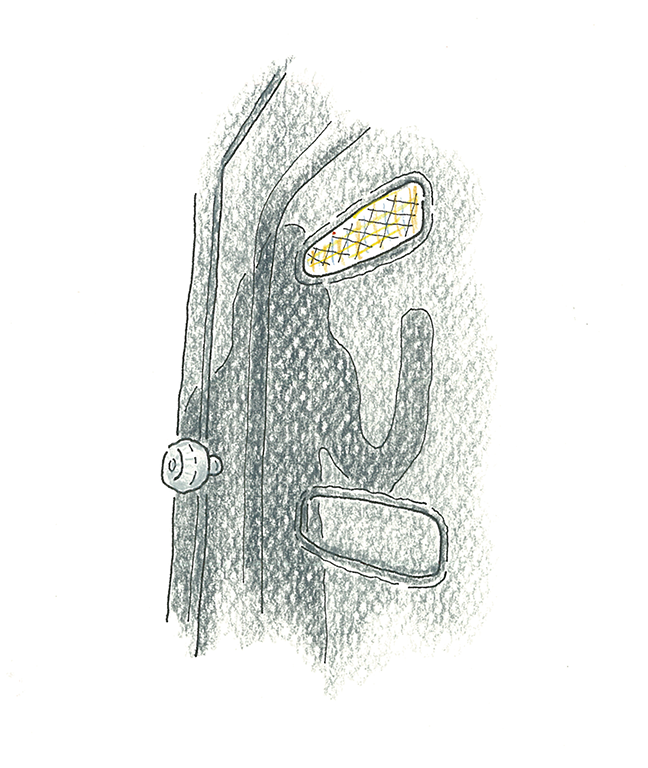
一連の記憶の断片の最後は
玄関の小窓から覗いた母の笑顔。
ブザーを鳴らさずに、扉を叩く音。
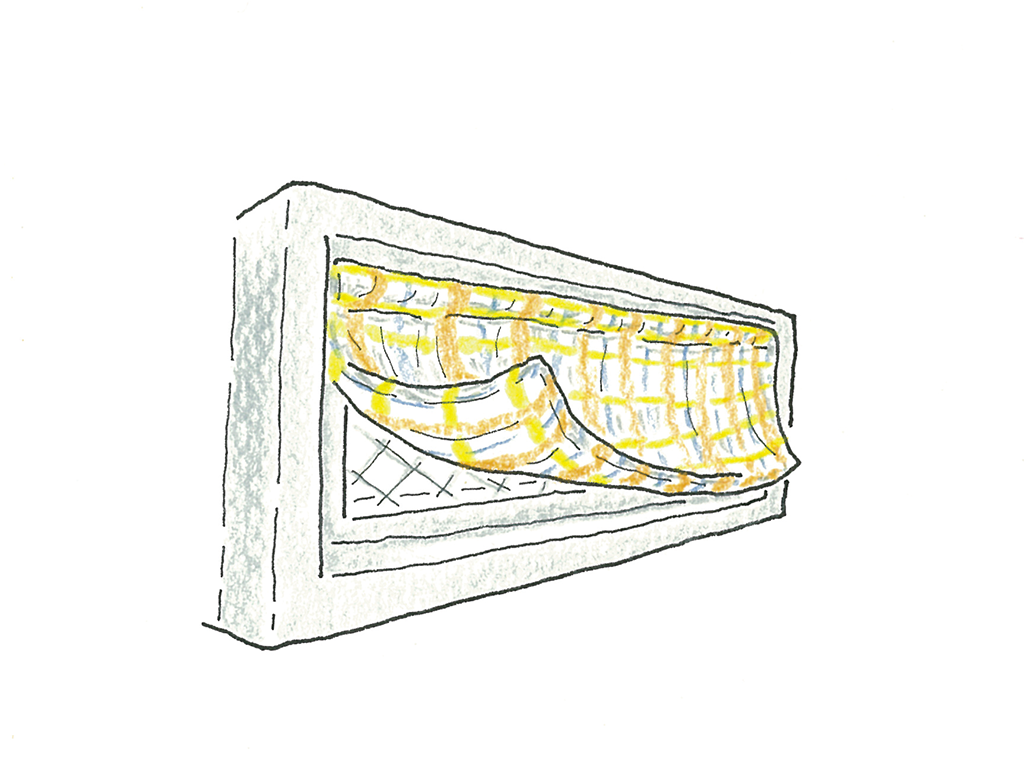
相手を小窓で確認してから
鍵を開けるように躾けられていた。
椅子を踏み台に代えた憶えは、
きっと一度目の時のもの。
母の作り付けた覗き窓用カーテンをめくる。
ガラス越しに飛び込むうれしさ。

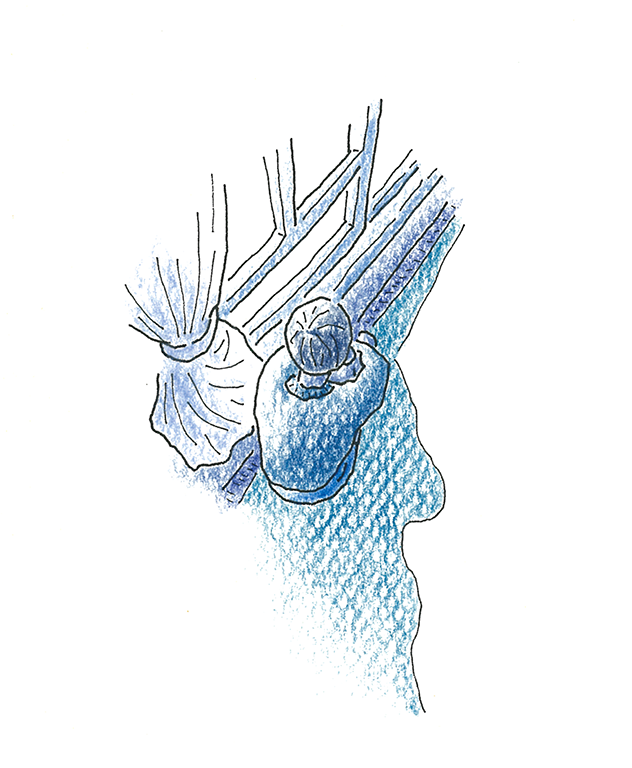
母がなぜいなくなり、
なぜ帰って来たのかを、わたしは
その時もその後も聞かなかった。
母も自ら口にしなかった。
人にはそういう部分もあると、
当時の母の年齢をまたいだ今は
なおさら思う。
責めるやなじる氣持ちなどは毛頭ない。
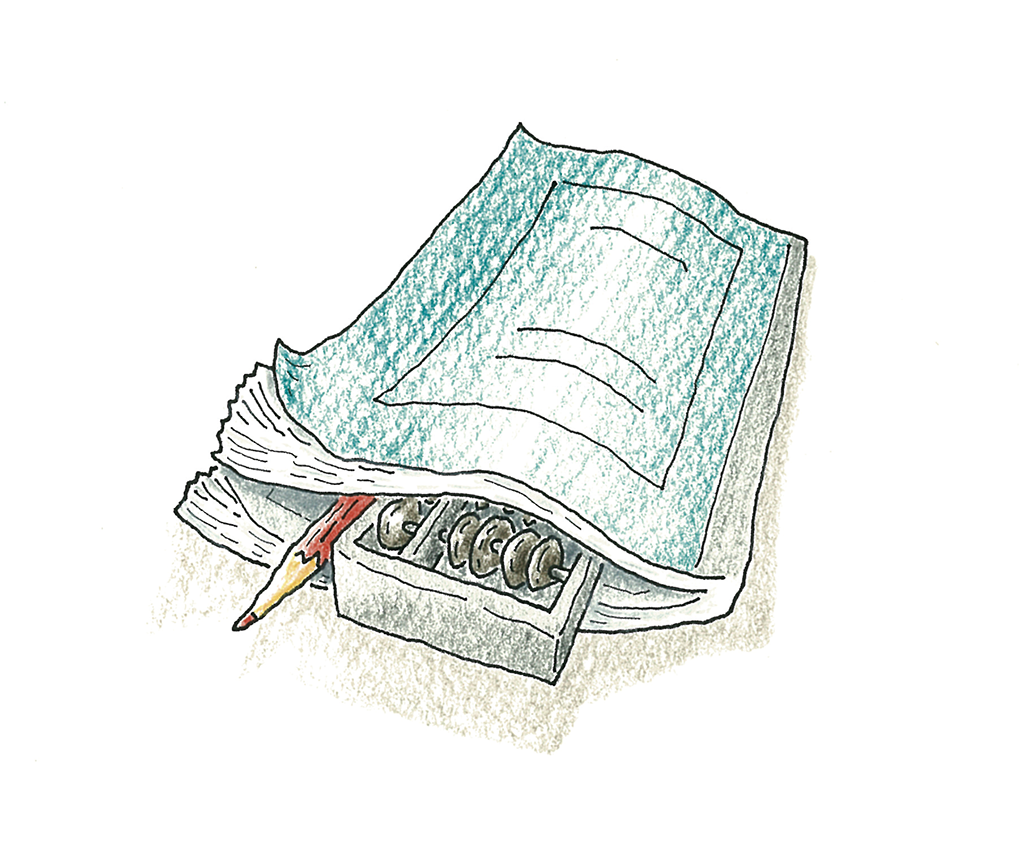
あの時のうれしさは現在も
わたしのうれしさの中で一番にある。
わたしはいろいろな犠牲と
諦めを強いただろうし、
たくさんの夢や時間や可能性を
奪ったはずにちがいない。
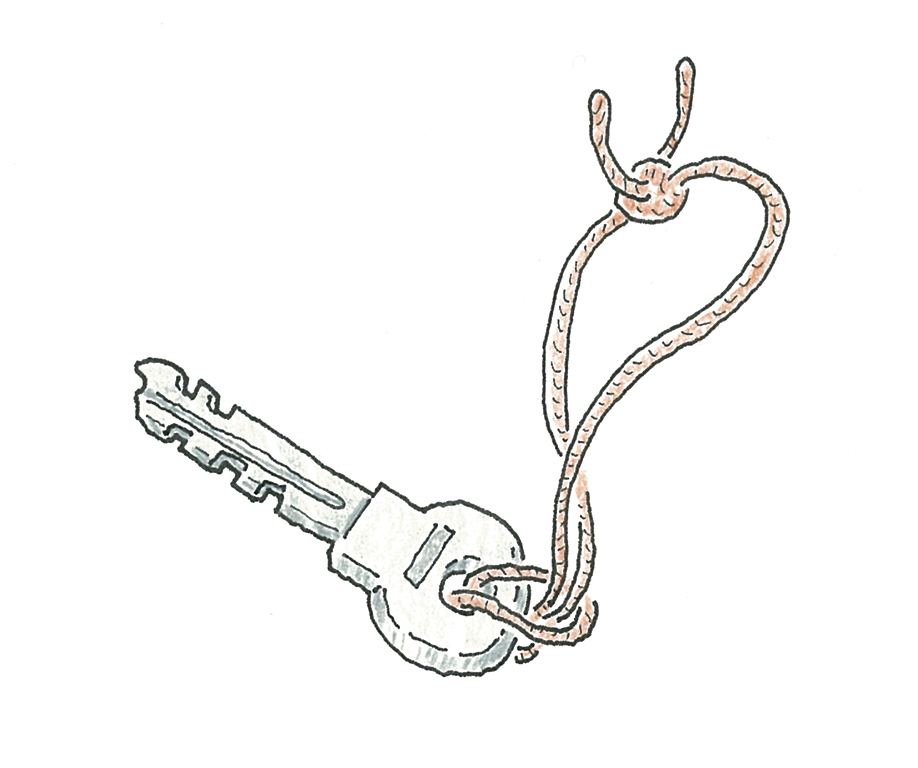
申し訳なく、ありがたい。
